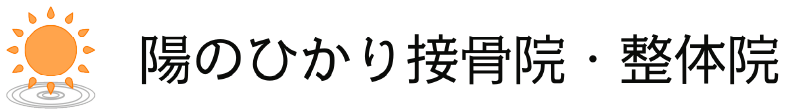こんにちは!四日市市塩浜にある
陽のひかり接骨院・整体院 女性セラピスト見並です。
前回は、五大栄養素について更新するつもりが
内容がもりもりになってしまい…。(笑)
三大栄養素についてまでしか、更新ができませんでした。
なので、今日は五大栄養素のうち、残り2つ
【ビタミン】【ミネラル】について投稿していきます。
ビタミン、ミネラルについては、過去にも類似した内容を更新しておりますので
そちらも読んでみてください◎
五大栄養素別 役割
五大栄養素のそれぞれの役割を簡単に説明したいと思います。
身体のエネルギーとなる栄養素 ⇒ 糖質・脂質
身体をつくる ⇒ タンパク質・ミネラル
身体の調子を整える ⇒ ミネラル・ビタミン
前の記事でもお話しましたが、糖質と脂質は
現代の食生活ではどうしても過剰になってしまうので
摂取量をコントロールすることが大事。
少なすぎても、エネルギー不足になりますし
過剰に摂取しすぎても、脂肪として蓄積してしまう可能性が高くなります。
タンパク質は、髪や肌、筋肉、爪など
あらゆる部分を作るのに重要な栄養素。
不足しては、健康や美容にも悪影響となりえます。
そして、【身体をつくる】【身体の調子を整える】役割をしている
ミネラルについて、解説していきたいと思います。
ミネラルについて
ミネラルは、体内ではほとんど作ることができず
食事やサプリなど、体外から摂取する必要があります。
主なミネラルは
| 名前 | 主な働き | 含まれる食品 |
| カルシウム | 骨や歯の形成、神経の伝達 | 牛乳、チーズ、小魚 |
| マグネシウム | エネルギー代謝、筋肉の収縮 | ナッツ類、豆類、海藻 |
| カリウム | ナトリウムとのバランスで血圧調整 | バナナ、イモ類、野菜 |
| ナトリウム | 体液のバランス、神経伝達 | 食塩、加工食品 |
| 鉄 | 酸素の運搬(ヘモグロビン) | レバー、赤身肉、ひじき |
| 亜鉛 | 免疫機能、味覚の維持 | 牡蠣、肉類、豆類 |
| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの材料 | 海藻類 |
| セレン | 抗酸化作用 | 魚介類、卵、ナッツ類 |
となります。
ミネラルに大事なのはバランス
ミネラルは単独で働くのではなく、お互いに助け合いながら働くため
バランスがとっても大事といえます。
カルシウムとマグネシウム
- バランスの理想的な比率は 2:1
- カルシウムは骨や神経に必要ですが、マグネシウムが不足すると、カルシウムが上手に働けなくなります
- カルシウムは筋肉を収縮させ、マグネシウムは筋肉を弛緩させる作用があるので、カルシウムを過剰に摂取すると筋肉が痙攣したりなどの症状が出やすくなります。
銅と亜鉛
- 銅と亜鉛の理想的比率は1:0.9~1
- 銅や鉄は不足すると貧血症状がでるため、摂取することが大事ですが、摂取しすぎると酸化ストレスを引き起こすため注意が必要です。亜鉛は、酸化ストレスを抑える作用があるため、バランスよく摂取することが大事です。
ナトリウムとカリウム
- 体内の水分バランス・血圧調整に関わる重要な関係
- ナトリウム過多(塩分過多)⇒高血圧のリスク増
- カリウムはナトリウムの体外への排出を助ける⇒野菜・果物をしっかり摂るとバランスが整う
ミネラルはお互いが協力してこそ効果を発揮するため
バランスよく摂取することが大事です。
色んな食材をまんべんなく摂ったり、偏ったサプリは避けたり、不足しがちな分を意識して摂るなどが重要といえます。
ビタミンについて
ビタミンは【身体の調子を整える】役割をしています。
こちらも体内ではほとんど生成されないため、食事から摂取する必要があります。
ビタミンには水に溶けやすい【水溶性ビタミン】と
油に溶ける【脂溶性ビタミン】の2種類に分かれます。
水溶性ビタミン(ビタミンB群、C)
体内に貯めておけず、余分な分は尿として体外へ排出されるため
過剰摂取の心配はないが、短時間しか体内にいれないため細めな摂取が必要。
| 名前 | 主な働き | 含まれる食品 |
| ビタミンB1 | 糖質のエネルギー代謝を助ける | 豚肉、玄米、大豆 |
| ビタミンB2 | 糖質の代謝、成長を助ける | レバー、卵、乳製品 |
| ナイアシン(ビタミンB3) | 皮膚や神経の健康維持 | 肉類、魚、ナッツ |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助ける | 鶏肉、バナナ、豆類 |
| ビタミンB12 | 赤血球の生成(貧血予防) | レバー、魚介類、卵 |
| 葉酸(B9) | 細胞分裂のサポート、妊娠中に重要 | 緑黄色野菜、レバー |
| ビタミンC | 抗酸化作用、コラーゲン生成 | 柑橘類、ピーマン、苺 |
脂溶性ビタミン
油にとけやすく、摂取しすぎると体内に蓄積しやすく過剰摂取の恐れも。
| 名前 | 主な働き | 含まれる食品 |
| ビタミンA | 視力・免疫力の維持 | レバー、人参、ほうれん草 |
| ビタミンD | カルシウムの吸収促進(骨を強くする)うつ病リスクの低下 | 魚、キノコ、日光浴(日を浴びると体内で生成できる) |
| ビタミンE | 抗酸化作用、老化防止 | ナッツ類、植物油、アボカド |
| ビタミンK | 血液凝固、骨の健康 | 納豆、緑黄色野菜 |
ビタミンのバランス関係
- ビタミンC+鉄 ⇒ 鉄の吸収を助ける(レモン+ほうれん草など)
- ビタミンD+カルシウム ⇒ カルシウムの吸収を助ける
- ビタミンE+ビタミンC ⇒ 抗酸化作用を高める(ナッツ+柑橘類など)
ビタミンも他の栄養素同様、バランスが大事。どれか1種類のビタミンだけを摂ると逆効果の恐れも。
水溶性ビタミンはこまめに摂取し、脂溶性ビタミンは過剰摂取に注意です。
まとめ
ここまで五大栄養素について前後編と分けて更新してきましたが、いかがでしたでしょうか?
普段自分に何が不足しているかが、そもそも分からないなんて方もみえると思います。
今はアプリなどで、食品の大体の栄養素が分かるものもありますので
それらを利用し、自分に足りない栄養素を知るというのも手かと思います。
以前別の記事でも書きましたが、食事で摂取するのが1番ですが
どうしても、全ての栄養素を食事から摂取するのも難しいと思います。
サプリは足りない分を効率的に補えるのでオススメです。
当院にも水溶性ビタミン系のサプリ等置いてありますので
気になる方は、一度ご相談くださいね◎